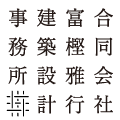床も均されスッキリしました。やはり、足元が良いと気分も良い。
さて基礎の補強工事は、続いて差し筋を入れていきます。
差し筋とは、コンクリートに差してあげる鉄筋の事を言います。
コンクリートは圧縮に強く、引っ張りに弱い。鉄筋は圧縮に弱いが、
引っぱりに強い。互いの長所を活かし初めて鉄筋コンクリートは
頑強な強度が得られます。
既存の基礎には鉄筋が入っておらず、大きな地震には耐えられない。
差し筋は、既存の基礎と新たな基礎とを一体にする為に入れます。

一般的な差し筋アンカーは穴を開け、鉄筋を叩き入れ、先が中で
穴の中で開く事で抜けなくなるもの。しかし、古い基礎に叩いて
入れるとコンクリートがひび割れして十分な強度を得られない。
今回使うアンカーは注入型接着系アンカー。穴に樹脂を注入し、
鉄筋を差し、樹脂が硬化することで鉄筋が抜けなくなるもので、
低温下でも使えて、施工性もよく十分な強度を発揮してくれる。

注入型接着系アンカーで計170本の差し筋を打ち込む。

続いて、土台のアンカーボルトの加工。大工さんに借りていた、
バーベンダーという鉄筋曲げの機械で曲げる。
土台のアンカーボルトは基礎からズレないようにする為のもの。
石積みの上の土台は、上からのアンカーボルトが効かない為、
羽子板ボルトで代用し新たに打つコンクリートに横から効かせる。


私の方での準備も整い、SK佐々木建設さんが鉄筋を組みにきました。
まずは、地面からの湿気を防ぐ防湿フィルムを砕石の上に敷いてから
鉄筋を組んでいきます。


差し筋、アンカーボルト、ホールダウン等は全てセルフビルド。
ケミカルアンカーは少々高価なので地道にコストダウンを図る。

半分解体してあった立ち上がりの基礎にも鉄筋を立ち上げておき、
スラブを打った後に、更に新たに基礎を抱かせるように補強する。

こうして、基礎の補強コンクリートスラブを打つ準備が整った。
コンクリートという頑強な構造物は失敗が許されない為、打つ前は
現場にはとても緊張感があります。確認作業も入念になります。

1月21日、大寒の日の朝、常盤坂の家に生コンのミキサー車が。
いよいよ、コンクリートの打設が始まりました。

SK佐々木建設からコテ均し1名、ネコ押し3名、そして私は、
バイブレーターの係で計5名の連携作業の始まりです。



コンクリートを流し、バイブレーターを掛け鉄筋の下や隅まで
均等にコンクリートが回るようにします。それから、木ゴテで
押さえ、最後に金ゴテで押さえて進んでいきます。

木ゴテで終わる仕様だったのですが、職人さんの計らいで金ゴテで
仕上げてくれました。 とても有り難い事です。


ミキサー車2台分、7立米のコンクリートを人力で打設しました。

冬場のコンクリートは打設後、大切に養生しなければなりません。
コンクリートは気温が低いと硬化時間が著しく長くなり、強度が
出るまでもとても時間が掛かります。
打設の完了と共に、ジェットヒーターを炊き続け、コンクリート
温度を2℃以上に保たなければなりません。そして、夕方から
晩にかけ、コンクリートの水が引いた頃に、もう一度、金ゴテで
押さえセルフにて仕上げていきます。下地が上手いので楽だった。

運良く、大寒にも関わらず、この日は最低気温が1℃と+の気温。
翌日も 最高気温が5℃と、この時期にしては異例の気温の高さで
コンクリートの硬化も早く進んでいます。


ジェットヒーターは6時間置きに1日4回、灯油を補給し続ける。
その為、夜中も現場に足を運び続けなければならない。同時に、
表面だけ乾燥が進むのを防ぐ為、コンクリートに水打ちも行なう。

2日目には、硬化も進み歩けるようになるが、それでもまだまだ
強度は出ていない状態。

コンクリートも生き物のようで、しっかりと水打ちをし潤いを与え
ていかなければ品質の良いコンクリートにはならない。
冬場の時期は、5日間は暖を取り水打ちを続けなければならない。

今夜から一気に−10℃まで冷え込むので、ジェットヒーターと
更に、練炭も炊きながら養生をしに行ってきます。
根気のいる作業はまだまだ続きます。